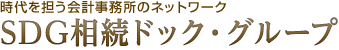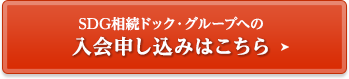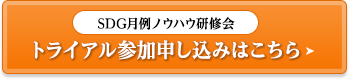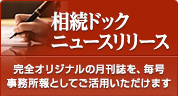| 税理士のためのマネロン対策(一般向け) |
2019.01.18

◆ なぜ、マネロン対策が必要なのか?
● マネロン対策の必要性
マネロンにはつぎの2種類があり、マネロン対策を強化するには各国の強調による世界的な対応が求められています。税理士といえどもその例外ではありません。
★ マネー・ローンダリング
マフィアなどの犯罪収益を資金洗浄し、捜査機関の操作などを逃れようとする方法です。
★ テロ資金供与
テロリストに、テロ行為(爆弾テロ・ハイジャックなど)の資金を表に出ない形で提供する行為を言います。
● 犯罪収益移転防止法の制定
日本では、2007(平成19)年にマネロン対策のため、犯罪収益移転防止法が制定されており、すでに11年を経過しています。
マネロンに際しては、「税理士(税理士法人含む)は、法律や会計の専門知識を持ち、社会的信用が高い」ため、税理士を取引に介在させて正当な取引であるとの外観を作り出すことが可能となります。そこで、税理士にも法律に基づいて一定の義務が課されているというわけです。
◆ 犯罪収益移転防止法における税理士の責務
税理士に課されている犯罪収益移転防止法(以下、犯収法)上の義務には、★顧客の・・・
● 犯収法上の税理士の義務
★ 顧客の本人確認義務
これはかなり重要で、取り扱いは個人と法人で異なります。ここでは、顧客が・・・
★ 本人確認記録の作成・保存義務
本人確認記録は作成が義務づけられると共に、7年間の保存が必要とされています。
★ 取引記録の作成・保存義務
取引記録についても作成義務があり、その保存は上記同様7年間とされています。
● 犯収法の適用対象となる取引
つぎのような特定受任行為の代理等を行う内容の契約を締結する場合は、犯収法の適用が生じます。
★ 宅地・建物の売買や手続き取引
★ 会社・・・ 取引
★ 200万円超・・・ 財産管理・処分取引
★ マネ・・・ 認められた取引
★ その他、顧客管理上・・・ 取引
SDG相続・ドックグループに入会されますと、上記記事の内容や添付ファイルはすべて閲覧いただけます。