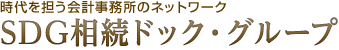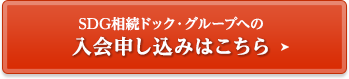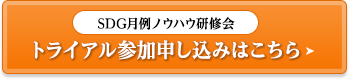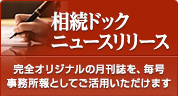| 税理士事務所も厚生年金の適用対象に!(一般向け) |
2020.01.14

対象となる人数は約5万人にも上る見通しで、業界に与える影響も少なくないものと思われます。
※税理士業界にとって重要な内容であるため、SDG会員以外のすべての方に全文公開対応しています。
◆ 今までの取り扱いはどうだった?
● 個人事業所は対象外!
顧問先企業では加入しているのが当然の厚生年金でも、税理士事務所は対象外とされ従業員を加入させる必要はありませんでした。
このため、従業員は自ら国民年金に加入して、老後資金の一部を確保する必要がありました。また事業主としての税理士は、結果的に、厚生年金加入時の事業主負担分(基本、保険料の1/2)相当額の人件費コストが軽減されていました。
税理士事務所は、法定16業種以外の飲食業や農林水産業などの”非適用業種”に含まれていたため、従来から対象外とされてきたものです。
● 加入すべき事業所は
厚生年金への加入が強制される16業種であれば、常用雇用者が1人以上いる法人と個人事業主でも常時5人以上の従業員がいれば、対象となっていました。
しかし、厚労省の今回の見直しにより、個人の税理士事務所は、”非適用業種”の見直しに伴い、常用雇用者が5人以上いれば厚生年金に加入する必要が生じる見込みです。
◆ 「士業」を適用対象業種とする理由など
長期低迷を続ける新規開業率、顧問報酬の低額化の波、募集しても人が集まらない現状などから、厚生年金への強制加入が実施されれば、税理士事務所経営はますます厳しさを増すばかりに。
● 税理士事務所が厚生年金加入対象となる理由
「士業」では、被用者保険適用関連の事務処理能力が期待できると共に、経営的にも比較的安定していることも含め、次の2つの要素を考慮して、見直しを決めたそうです。
★ 個人事業所の割合が高いこと
「士業」では、法人化率が低く、個人事業所の割合が高いうえ、常用雇用者数が5人以上の割合が他業種に比して高く、被用者として働きながら非適用となっている人が多いと見込まれる。
★ 制度上の法人化への一定の制約条件があること
法人化に法規制上の制約や法人化が不可能であることなどのため、他業種なら法人化している規模でも個人事業所のままとなっている比率が高く、被用者保険制度上で個別対応を図る必要性が高い。
この結果、具体的に・弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・香粧品・海事代理士を適用業種とする見直しを行うことに。
● 「士業」に占める個人事業主の割合
「士業」の全事業所に占める個人事業所の割合は90.7%と、2番手以下の洗濯・理容・美容業76.8%、飲食サービス業の61.9%に比べ、断然高い状況にあります。
また、個人事業主で従業員数が5人以上の事業所では、「士業」が全体の12.3%、飲食サービス業が6.7%、以下娯楽業などの2.5%程度が続いており、「士業」の規模は個人事業所全体の中では際立って大きいことが判明しています。
税理士事務所が厚生年金の適用対象事業所に含まれることに伴い、有用性の高い人材確保のためにも、こうしたコストを吸収すべく対応を図らねば生き残れない時期に入ったようです。
SDG相続ドック・グループに加入されますと、会員専用の上記関連資料(厚労省年金局など)をご覧いただけます。加盟のお申し込みは、欄外の赤ボタンをクリックして手続きをお進め下さい。
なお、SDGグループは税理士・会計士のための団体で、他業界の協賛など一切いただかない独立団体です。